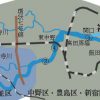「江戸っ子のうまれぞこないかねをため」とか「江戸っ子は宵越(よいご)しのぜには持たない」という生き方は、貯金がないと不安なわたしのような小心者にはできません。司馬遼太郎は「街道をゆく36 本所深川散歩 神田界隈」(朝日新聞社)で、この生き方は職人のこと、金がいくさの矢弾となる商人のことではない、としています。腕でめしを食う職人が金をためると、腕をみがくことをわすれ、いつまでも腕のあがらない職人となる、といったことなのでしょうか。金よりも腕を大切にする職人の生き様だったようです。
神田生れの生粋の江戸っ子、五代目古今亭志ん生(明治23年(1890)昭和48年(1973))はそんな生き方をしたひとです。金よりも芸を大切にした人生でした。自伝「なめくじ艦隊 志ん生半生記」(日本人の自伝 21、平凡社(金原亭馬助記、昭和31年(1956)朋文社刊の再版))では、結婚して1ヶ月半で、妻のりんさんが持参したお金、箪笥(たんす)、長持、琴などをスッカラカンにしちまった、と自慢げに話しています。仲間との遊びに使ってしまったのです。自分には芸がある、だからだまってついてこい、といったところなのでしょう。
金があれば使ってしまう、そのために貧乏な暮らしが長く続きます。後年、娘の美濃部美津子(みのべみつこ:作家)さんが
「お母ちゃん、よく別れようと思わなかったね」
とりんさんにきくと、
「箸(はし)にも棒にもかからない人だったけど、落語を捨てなかった。稽古(けいこ)は一生懸命だった。こんなにやってるんだからいつか立派になる、と思った」
と、しっかりした口調で答えたそうです。
こんな夫婦が江戸にはあふれていたのでしょうか。志ん生の生き様を駆け足で訪ねた、12kmウォーキングでした。
参考サイト:これが志ん生だ、『おしまいの噺』(1)志ん生、志ん生とりん―東京・日暮里、よしみの青春日記、上野小学校
![]()
1.浅草
明治23年(1890)に神田(東京府神田区亀住町:現・千代田区外神田五丁目)で生まれた志ん生は、子供の頃に浅草(浅草区永住町一二七:現・台東区元浅草二丁目、その後、浅草通りをはさんで反対側の下谷区北稲荷町五一:現・台東区東上野五丁目)に移っています。「その時分の浅草には、あやしげな銘酒屋なんてものがあって、箸(はし)にも棒にもかからねえようなやくざ者がウヨウヨしていたんです。そういう環境なんで、ろくなことはおぼえない」、やがて家をとびだし無頼の生活をおくるようになります。明治38年(1905)15歳のときです。
多感な少年時代に大きな影響を与えたこの町は、わたしが高校、大学時代に住んでいた町です。わたしのころは「やくざ者がウヨウヨ」といったことはありませんでしたが、志ん生が子供のころはまだ江戸の面影を残す町、ぶらぶらしているやくざ者でもなんとか暮していける町だったのでしょう。志ん生が通った下谷尋常小学校の校歌(*1)からも、「いざやめでん(賞美しよう) さくらばな」といった当時ののんびりぶりがうかがえます。
(*1)
下谷小学校校歌 鳥居 忱 作詞 上 真 行 作曲 明治29年11月25日制定
一
春のしのぶの 岡の辺や
朝日ににおう さくらばな
花の盛りは のどやかに
かおりにこもる 学びの舎
いざやめでん さくらばな
二
春のうららの 浦安(日本国)の
くにのすがたの さくらばな
花の光を うけつつぞ
人の心も のどかなる
いざやめでん さくらばな
2.上野鈴本亭
七つか八つのころ、父親に連れられてよくきた寄席です。何か買ってもらえるから喜んでついていった、と言っていますが、寄席の楽しさをからだで吸収した時期だったのでしょう。噺家志ん生誕生の原点となった演芸場ともいえそうです。鈴本のある上野広小路は、火除地(*2)だった広い空地が人びとで賑わう盛り場となったところで、そんな楽しい場の印象も子供の心に深く刻みこまれたにちがいありません。
(*2)
焼死者十万七千人という、江戸史上最大の大火「明暦の大火」(通称”ふりそで火事”:明暦三年(1657))をきっかけに、”上野広小路”のような広い”火除地(ひよけち)”がいくつか設定されました。
ちなみに、志ん生が所帯をもってから住むことになる「なめくじ長屋」の本所は、このときに、旗本・御家人(ごけにん)といった直参(じきさん)の移住先として開発されたところです。本所は低い土地だったために、多くの運河を開削し、水捌(みずはけ)をよくするとともに、掘った土で地面を盛りあげました。池を掘った土で地面を盛りあげていた武家屋敷もあったようで、「なめくじ長屋」を建てるために埋めたてた池とは、そんな武家屋敷の池だったにちがいありません。
3.田端
大正11年(1922)32歳でりんさんといっしょに住みはじめ、やがて結婚すると田端(北豊島郡滝野川町大字田端一八五:現・北区田端一丁目)に移転します。収入もないのに遊びにでかける志ん生に「行ってらっしゃい」と下駄をそろえるりんさん、そんな暮らしがつづき、やがて家賃がたまって「これまでの家賃はいらないから、出ていっておくれ」と追い出されてしまいます。
このころの田端は、芥川龍之介や菊池寛などが住む、高台にある文士芸術家村ともいえるところでした。そんな地から、市内から遠く離れた笹塚(豊多摩代々幡町大字笹塚:現・渋谷区笹塚)へと移るのです。都落ちの心境だったことでしょう。田端移転3年後の昭和元年(1926)36歳のときです。
4.なめくじ長屋
その後も家賃が払えずに笹塚近辺での転居をつづけ、田端から5回目の転居で本所業平(なりひら)(本所業平橋一丁目一二:現・墨田区業平一丁目)の長屋に移り住みます。昭和3年(1928)38歳のときです。
大正12年(1923)の関東大震災直後に池を埋め立てて急造されたおそまつなバラックで、ちょっと雨が降ると、あたり一面海のようになり、家の中にも水が入ってくる、壁にはそんな洪水の跡がある、20軒ほどの長家で、新築当初入居していた人たちはみんな出ていってしまいました。噺家(はなしか)が住んでくれれば入居者がまた集まってくるのでは、という大家さんの思惑から家賃がタダだったのです。
夜、電気をつけると、まわりが空家でまっ暗なため蚊の大群が押しよせ、蚊柱がたち、口の中にまで入ってくる凄まじさで、足の長いコオロギやノミもみんな集まってくる、そのうえ十センチ以上もある茶色がかった大ナメクジが、あっちからもこっちからも押しよせてくる、そんな長屋でした。
昭和11年(1936)46歳で永住町(現・台東区元浅草)に引っ越すまでの8年間をここですごします。
「そのうちにこの長屋にも、だんだん人が入って来ましたが、こういうところに入ってくる人はだいたい似たりよったりの人種で、くらしはみんな楽じゃない。それだけにみんなよく気があっていましたね、たのしいもんでしたよ。(中略)だれかが、からだの工合でも悪くなったというと、まわりのお神さんたちが、みんなドヤドヤやって来て、医者へとんで行く、湯タンポをこしらえる、自分のうちにある薬をもってきて服(の)ませる。苦労をつんだ人が多いから、みんな人情があたたかく、同情心がふかい。おたがいに理解しあい、助けあっていく。だから、ああいうところで暮したときのことが、今だってなつかしく忘れることができない」
としみじみ語っています。
こんな心底からの言葉には凄みすら感じます。彼の噺が人びとの心をとらえるのも、そんな暮らしがあったからこそなのでしょう。
5.谷中の諏方(すわ)神社
昭和22年(1947)57歳で慰問先の満州から帰国し、昭和26年(1951)61歳で日暮里(荒川区日暮里町九丁目一、一一四:現・西日暮里三丁目)へ転居、昭和36年(1961)71歳のとき脳出血で倒れ、昭和48年(1973)9月21日83歳でこの日暮里で亡くなりました。帰国してから倒れるまでが志ん生の全盛期で、独演会はいつも満員で、つねに客をわかせていたといいます。貧乏ぐらしからやっとぬけだしたのもこの時期だったそうです。
どんなに売れても、売れない時代と変わらずに毎日稽古していた志ん生の稽古場が、家から300メートルぐらい歩いたところにある諏方神社でした。細い坂道を登りきって車が通れるぐらいの道にでたところにあり、神社の裏手が崖で、崖下をJRが走っています。その崖っぷちにおいてあったベンチで稽古をしていたそうです。人がまったく来ないので、稽古にはもってこいの場所だったといいます。
静かな神社を歩いていると、いまのわたしよりも高齢だった志ん生が毎日稽古に励む姿が目にうかび、なにか元気付けられるおもいがしました。
6.終焉の地
亡くなる前の晩です。りんさんは2年前に74歳で亡くなっていて、長女の美津子さんが付き添っていましたが、その美津子さんに大好きなお酒をせがみました。どうしてもという志ん生に、吸いのみにいっぱいのお酒を飲ませてやったそうです。
「あんなに『おいしい、おいしい』って飲んだことはないんです。普通のときは、飲ませても『うまかった、もう、いいよ』っていうだけで、それが、ものすごく『おいしい』といったんです。感無量に……。私もなんとなく、『そんなにおいしくてよかったねえ』っていって『ウーン』って、満足して寝たんですよ。それが最後で、末期の水は、やっぱり、お酒でしたね」
と美津子さんが語っています。次の日、静かに眠るようにして亡くなりました。
志ん生宅は大手不動産会社所有で、志ん生が亡くなると一家は立ち退きをせまられたようです。現在は、志ん生とは無関係なマンションが建っています。あんなに売れていても家は持たなかったのでしょうか。江戸っ子志ん生らしさともいえそうです。
「なめくじ艦隊」にみる志ん生の半生は、金や物は貧しくても、心がとても豊かな印象を受けます。成功した志ん生だからこそかもしれませんが、うらやましさすら感じます。そんな人びとが暮していた、暮していけた江戸は、意外と居心地のよいところだったのではないでしょうか。