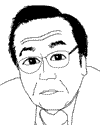ソ連という国で、300万点もの日本関連機密資料の中から1通の手紙を探し出し、その手紙について証言できる人物からの裏を取るために、厳寒のソ連で21日もの間その人物の家の前で毎朝たたずんだジャーナリスト加藤昭(かとう あきら:1944年静岡県生まれ)氏の執念や集中力にただただ驚いた講座だった。
暴力革命を否定し人格者と当時言われていた日本共産党野坂参三が、スターリンに日本共産党員を密告し処刑させていた密告者だったことをスクープした「闇の男野坂参三の百年」(週刊文春(1992年9-11月)に連載されたドキュメントをベースに文藝春秋社より1993年に発刊)の取材エピソードだ。このドキュメントにより野坂参三は日本共産党を追われ、この本を読んだ日本共産党員の多くが涙し党員をやめていった。
この取材エピソードの詳細は感動的だ。ジャーナリストという人たちはそこまでやるのかとさえ思う。フリージャーナリスト加藤氏が何の当てもなくモスクワに一人で到着するところから、現地での調査スタッフを集め、300万件もの機密文章の閲覧に成功し、スタッフの努力とチームワークで1通の英文の手紙を見つける。そしてその手紙の裏をとるためにソ連対日政策の総帥といわれた人物への接触を試みる。それが冒頭にある「厳寒のなかでの毎朝のたたずみ」となる。イワン・イワノビッチ・コワレンコというその人物の名前を加藤氏は白板に大きく書いた。氏の強い想い入れを垣間見る。毎朝顔を合わせて頭を下げるだけの加藤氏に、21日目にコワレンコから声を掛けてきた「いったい何を聞きたいんだ」と。そして長時間のインタビューの中で全てを語ってくれたのだ。
フリーのジャーナリストである加藤氏にとって結果が出なければ何の収入にもならない。ソ連の戦闘機にサハリン沖で撃墜された大韓航空KAL007便事件では2年半調査し、サハリンにも行ったが大きな結果は得られず60万円の原稿料となっただけだった。2年半で僅か60万円の収入だ。日本共産党について調べようとモスクワに降り立ったときも「結果がでないかもしれない」という大きなリスクをかかえていた。それでも突き進むのはジャーナリズムの現場の面白さが忘れられないからのようだ。今回の話の中でもエピソードの区切りごとに「面白いですね」とい言葉が頻繁に出てきた。苦労した中で成し遂げた達成感は「面白いですね」という表現になる。花田編集長からも「面白い」という言葉をよく聞く。「面白い」というのはジャーナリストの力の源なのだろうか。
加藤氏がジャーナリストを目指すきっかけとなったのは、学生の時に参加した「大宅マスコミ塾」でジャーナリズムの面白さにはまったことだった。講座初日の大下英治氏と同じだ。こういった全く異なる個性の人たちをジャーナリズムに目覚めさせた「大宅マスコミ塾」とはすごいところだったのだ。塾の中間試験は「38度線に行って取材してこい」「アメリカに行ってケネディ長官のインタビューを取って来い」「ベトナム戦争を取材して来い」といったスケールの大きなもので、大学での授業とは比べものにならない面白さで若い加藤氏の心をとらえた。マスコミ人として大切なものは「友人」「読書」「旅」、と塾では教えていたそうだ。
共産党一党独裁の長期化、言い換えると権力の長期化が大きな腐敗を生むのを自分の目で見てきた加藤氏は「マスコミは常に権力の反対側にいなくてはいけない」という。物静かな細身の加藤氏の内面にある激しい情熱や信念に圧倒された講座だった。この1講座だけで「マスコミの学校」を受講した意義が十二分にあったといえるほどだ。質問コーナーで加藤氏が「ソ連行きは『日本共産党を書かないか』という花田さんからの1本の電話から始まった。花田さんはそれ以上のことは何も言っていない。皆さん、楽をしたいと思ったら編集者の方がいいですよ」と冗談を言うと、花田編集長は苦笑いしながらも「(編集者としての)感ですよ」とちょっと自慢げだった。