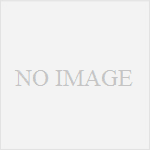2006年1月5日発売での「上海日本総領事館領事自殺事件」のスクープや先週2月16日発売「紀子さまご懐妊宮中(奥)全情報」特集の完売など勢いづいている週刊文春の編集長鈴木洋嗣(すずき ようじ:1960年東京都千代田区生まれ)氏には、他の週刊誌とは異なる戦略で文春を引っ張っていこうという強い意欲が感じられた。
1ヶ月にわたる専任体制での取材結果である「領事自殺」記事では、発売後に新聞各社がこれを追いかけるという大きなスクープとなった。そして、宮中専任記者のここ数年の活動結果ともいえる「宮中(奥)全情報」は旬の内容で、同日発売の週刊新潮50周年記念号の過去を振り返る内容との鮮やかな対比となる。取材にネクタイ着用は当たり前、と「火曜サスペンス劇場」に出てくるごろつきのような週刊誌記者イメージを否定し、「週刊誌のイメージを払拭しつつある」と自負する鈴木氏が率いる週刊文春はこれからますます面白くなりそうだ。口調は優しく、静かだが、強い信念と視野の広い戦略をもった編集長だ。
新米記者のとき先輩に言われた「記者となれば面会を申し込めばたいがいの人に会うことができるが、それは記者自身が偉いからではなく、記者が多くの読者を代表しているからだ」という言葉と、編集者のときに担当した司馬遼太郎氏から言われた「人の心臓をえぐりだし、その血の滴る様をも書くリアリズムこそ大切」という言葉が氏の心に強く残っているという。子供を殺された親にその思いなどを尋ねることなど普通はできないが、読者の代表だと考えると聞かざるを得ない。しかも本音のリアルな言葉を。ジャーナリスト活動の中で、先輩と司馬氏の言葉は鈴木氏の心の支えでもあるようだ。
ライターの資質につても語ってくれた。ライターの仕事は取材と執筆で、取材はその人に見合った「等身大」での取材しかできないし、執筆はその人の「見立て」での執筆しかできない。「見立て」とは「取材したことから本質を搾り出す作業のこと」のように説明されたが、言葉通り「執筆者の理解、考え、見方」ともいえるのではないだろうか。取材は食材集めで、書くということはその食材を料理することに似ている。同じ食材でも、サラダにするのか、カレーにするのかは料理人しだいということになる。スクープを連発する記者に「なぜそんなにスクープをものにできるのか?」と質問したところ、「人は喋りたいものだ」という言葉が返ってきたという。「上海総領事館領事自殺」も、1年もの間、自殺をひたすら隠し、自殺に追い込んだ中国に対して何の抗議もしない外務省、しいては日本政府への義憤がきっかけだという。それを聞きだせるか否かが取材側の力量となるのだろう。そして執筆のための「見立て」は、考えて、考えて、考え抜くことが重要だという。
最大級の発行部数を誇る週刊誌の編集長は礼儀正しく、真面目で、人の意見を聞きながら仕事を進めていくタイプのように見えた。高度成長期を走り抜けたカリスマ文春元編集長と低成長期を行く文春現編集長の会話を聞きたかったが、花田編集長不在のため実現しなかった。