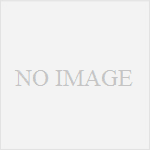「週刊文春」の記者として多くの事件を追いかけてきた佐々木弘(ささき ひろし:1936年生まれ)氏の話は、鮮度が命の事件取材における素早い判断力と行動力の大切さを教えてくれた。人生の大半を事件取材に費やし、日本全国はおろか海外50カ国以上を歩き回った氏の記者としての嗅覚は経験と共に磨かれていったようだ。
立教大学助教授・教え子殺害事件が起きたのは1973年、佐々木氏が37歳の時だ。たまたま見ていたTVの画面に「伊豆・石廊崎で一家心中」の1行テロップが流れ、すぐ下田に向かった。石廊崎であれば宿泊したのは下田だろうと考えてのことで、テロップを見たのが午後3時ごろ、下田に着いたのが夕刻という素早さだ。この尻の軽さ、野次馬根性こそ大切と氏は言う。心中したのが立教大学助教授一家4人であることを下田で知り、更に助教授が甲府出身の教え子との恋愛関係で悩んでいたこと、その教え子が行方不明であることなどを知る。そこで下田から甲府に移動し、甲府駅前の商店街を一軒一軒訪ねて立教大学に通う娘さんのいる家を探した。立教の現役大学生で甲府出身者はそんなにはいないだろう、とのもくろみだったと氏は言うが、「干草の山から針を見つける」ような作業だ。理屈で詰める前に行動する、とにかく足で稼ぐということだろう。幸いその日のうちに該当する家を見つけ、しかも娘さんは最近行方不明になっていると聞く。結局、その娘さんは助教授に殺されていたのだが、両親も佐々木氏も当然まだ知らない。そんな中での、両親へのインタビューとなる。誰も報道していないことを1番乗りで報道する記者の興奮や達成感が伝わってくる。
支社や記者クラブといった多くの縛りがある新聞記者とは異なり、どこであれ、だれであれ、いつであれ、飛んでいって取材できる週刊誌記者はとにかく面白い、と佐々木氏は言う。「佐々木さんに頼めばだいたい話をとってきてくれる」と花田編集長が紹介したが、事件の関係者を捜しだし、当人が話したくない話を聞きだすのは容易なことではないだろう。だからこそそれを成し遂げたときの達成感は大きく、「面白い」という言葉になる。暖かで気のいいおじさんといった、人に警戒心を起こさせない風貌と、当事者と同じ目線での、人を圧することのない言動が数々の事件を記事にできた大きな要因に違いない。