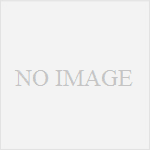正力松太郎、中内功といった昭和の怪物たちを描いているノンフィクション作家佐野眞一(さの しんいち:1947年東京生まれ)氏は、厳格な頑固親父といった風貌をもち、静かで気迫に満ちた語りで受講生をひきつける。氏ご自身も怪物で、怪物が怪物を描いたとさえ思う。
「正力は新聞やテレビをマス・メディアに仕上げ、野球やプロレスを国民的スポーツに押し上げた。我々は今でも正力の手のひらの上で過ごしているようなものだ。『巨怪伝 : 正力松太郎と影武者たちの一世紀』(1994 文芸春秋社)で正力を書いた後に、渡辺恒雄を書いて欲しいといわれた。ふざけるな!!渡辺が悪いというわけではないが(格が違う)」と一刀両断に切り捨てる言葉には、自分の仕事を『知の格闘技』と位置づけ、格闘しがいのある人物や事件を長年追ってきた佐野氏の一徹さが感じられた。
佐野氏が現在執筆中の「齋藤十一(2000年12月86歳で没)」は特に思い入れのある作品となるようだ。新聞社の週刊誌が圧倒的強さを誇っていた時に雑誌社から初めて発刊された『週刊新潮』、これをトップクラスの週刊誌にまでに育て上げた辣腕編集長、『週刊新潮』の「法王」とも呼ばれた齋藤十一氏の物語だ。彼は、瀬戸内寂聴氏など多くの作家を世に送り出した反面、その何十倍もの作家を葬ってきた。面白くないと大家の連載でも一回で打ち切ろうとする。血も涙もないと言われた齋藤氏のもとで多くのライターや作家が血のにじむような努力をしてきた。佐野氏もその一人だ。「人間は誰でもひと皮むけば、金と女と名誉心が大好きな俗物」と公言し、好きとか嫌い、良いとか悪いとかを超越した人間の真実に迫ろうとする文学活動のようなジャーナリズムには多くの異論もあるが、佐野氏は「齋藤のおめがねにかかったことは、私の誇りだ」と胸を張る。
表題の「いい話をどう引き出すか」は一言ではいえないが、最も大切なことは「聞き手の立ち位置」だ。「他人のことは考えるな。自分が何が欲しいか、自分が何を知りたいかだけを考えろ」というのは齋藤編集長がスタッフに飛ばしていた激だが、こういった聞き手の確たる『立ち位置』がなければ話は引き出せない、と佐野氏は説明する。聞き手の資質、力量によってどんな話が引き出せるかが決まるといったことも話していた。花田編集長から与えられた表題を真正面からとらえて説明しようとする佐野氏に、真面目さとプロ根性をみた。