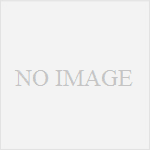ノンフィクション作家小松成美(こまつ なるみ:1962年神奈川県横浜市生まれ)氏の、会社員から作家になった今日までを垣間見ることができた。24歳の会社員のときにメニエル症候群によって救急車で運ばれる事態となり、「自分のこの一瞬はもう取り戻せない。自分のやりたいことをやろう」と決意し文章を書き始める。「13年間ノンフィクション作家を続けることの苦しさ、犠牲、忍耐、努力は並ではない」と語る小松氏はまさに努力、努力、そして努力の作家だった。
『中田英寿 鼓動』(幻冬舎文庫)、『イチロー・オン・イチロー』(新潮社)など、渾身の取材による作品を多く執筆している小松氏は、インタビュー前は「世界で一番この人のことを知っているインタビューアーでありたい」とありとあらゆる資料を読み、インタビューではこれらの資料によってフィルターがかからないように白紙の心で「世界で一番この人のことを知りたい」と臨む。執筆に人生を賭けている小松氏が、スポーツや芸術に人生をかけているアスリートやアーティストに真剣勝負で臨むのだ。そんな真摯な姿勢がインタビューを受ける一流プロたちとの共感を生み、感動的な作品が生まれるのだろう。
会社員を辞めて文章を書き始めてから5年後に原稿用紙30枚というインタビュー記事執筆の依頼を受けた。初めての大きな仕事だ。インタビュー相手は当時プロ野球のスーパースター近鉄野茂英雄で、大のインタビュー嫌いで無口だといわれていた。十分に下調べをしたうえでインタビューに臨んだが、1時間半に及ぶインタビューは悲惨なものとなった。調べ上げた多くのことを野茂に質問としてぶつけても表情のないまま「まあ、そうですね」といった回答が返ってくるだけで、自分の気持を言葉にはしてくれない。1時間半の90%は小松氏が喋っているというものだった。
暗澹たる思いの小松氏がインタビュー終了の5分ぐらい前に、野茂が三振を取るたびにフアンが「K」(三振の意味)と書かれた板を振る「Kボード」応援についてふと聞いてみた。観客が投げ放ったKボードで子供が怪我をしたことで全面禁止となっていたときのことだ。「Kボードが禁止になって残念ですね。大リーグみたいでカッコよかったのに!」と小松氏が言うと、「そうなんですよ。僕が三振を取る励みになっていたんです」という応答があり、そこから話が弾みだした。結局、野茂自身が電話で球団広報部と交渉しインタビューは更に1時間半続けられ、そこでの野茂は雄弁だった。前と同じ質問にも今度は多くを語った。1つの話題で流れを変えることができたは小松氏の努力と気迫を野茂が感じていたからに違いない。一流プロの心の琴線に触れ、心の言葉を引き出すノンフィクション作家がこうして誕生した。
野茂のインタビュー記事以前は、雑誌の小さなコラムなどを執筆していた。原稿用紙3枚を10日ぐらいかけて書き、編集者に渡すと「面白くない。タイトルも付けられない」と言われたり、全面真赤な修正が入ったりする。必死で書き直して再提出するという状態が続く。この時に「原稿を書くことの尊さと厳しさを知った」と小松氏は振り返る。多くの編集者に育てられたと感じているようだった。
「原稿を書くことほど苦しいことはこの世の中にはない、と断言できる」とか「これが世に出たらもう消せない。そんな重圧で眠れないときもある」と語る小松氏だが、中田英寿やイチローとのインタビューエピソードになると生き生きとして実に楽しそうだ。身振り手振りをまじえ、豊かな表情で熱く語る姿はまるで若い娘さんのように見えた。この心の若さと熱意が小松成美作品を生む原動力の一つなのだろう。