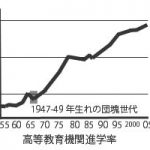樋口一葉の「たけくらべ」の舞台となった浅草吉原界隈を、物語の場面を想像しながら歩いてみました。読書とウォーキングという好きなことを組み合わせて、それぞれを倍楽しもうという魂胆です。おかげで、最後まで興味深く読み、何気ない風景も楽しみながら歩くことができました。
母が生まれ育った浅草は義理人情の下町、という漠然としたイメージでしたが、「たけくらべ」によって私のなかでより鮮明なものとなりました。『お前の父さんは馬(付け馬:客に付いて回る遊興費の取立て役)だね』(『』内は「たけくらべ」より)と子供でも知っているほど、親の仕事ぶりや家族の暮らしぶりがみんなに筒抜けで隠し事ができない町、『一軒ならず二軒ならず』多くの家族が酉の市の熊手作りに関わり『住む人の多くは廓者《くるわもの》(吉原で働く従業員)』と、みんながどこかでは仕事でつながっている町、祭りとなれば子供といえども『そろひの裕衣《ゆかた》』と団結力が強く、『帶は腰の先に、返事は鼻の先にていふ物と定め、にくらしき風俗』の子供でも鳶(とび)の頭の子であれば子供組の大将となる序列のはっきりした町、そんな町だったようです。義理人情は、そういった環境で人々がうまく暮らしていくための知恵だったような気がします。人々の暮らしぶりや関係が変わってきた現在では、義理人情も薄らいでいるのではないでしょうか。
母が生まれたのは物語の20年ほど後ですが、同じような様子だったに違いありません。近所は熊手作りではなく鼻緒作りで、母は鼻緒のミシン縫いをしていて結婚当初は父よりも稼いでいたというのが母の自慢でした。米や醤油がなくなれば隣に頼るのは当然だった、近所何軒かの分業で鼻緒を作っていた、祭りのためにみんな仕事をしていたようなものだった、鼻緒作りの元締めは大切だった、などという叔母の話と「たけくらべ」とが微妙に重なります。とても身近な物語として興味深く読むことができたのです。
ウォーキングで最も興味深かったのは美登利が住んでいた大黒屋寮のあった場所です。時雨の中、鼻緒を切って難渋している人を大黒屋寮の家の中から見かけた美登利が布の切れ端を持って門のところまで出て行き、その人が想いを寄せる信如であることを知って立ち尽くす、信如も後ろに美登利がいることに気づき動けなくなる、顔を合わすこともなく、言葉を交わすこともなく時間だけが過ぎていく美しく切ないシーンはこの物語のクライマックスともいえます。その舞台となったところです。
大黒屋寮のモデルだといわれている松大黒寮は吉原の揚屋町の跳橋近くにありました。当然のことながらその場所に当時の面影は微塵もありません。吉原を囲っていたお歯黒どぶ、それに架かる跳橋、簡素な格子門のある寮などを想像し、浅草田町の姉のもとへ行くとき、通らなくてもすんだ大黒屋寮の前の道をわざわざ歩いていた信如のいじらしさを思い、中田圃(なかたんぼ)にある太郎稲荷に朝参りしていた美登利も通らなくてもすんだ信如の住む龍華寺前の道をわざわざ歩いていたかもしれないなどと考えながらたたずんでいました。いつものウォーキングにはない楽しさが加わったのです。
物語の舞台の多くは一葉が営んでいた駄菓子屋の近所にあり、身近な人々を見つめながら「たけくらべ」を書いていることがわかります。また、一葉宅跡裏手にある一葉記念館には、いくつかの異なる構成での下書き原稿などが展示されていて、一葉がいかに考え抜いてこの物語を創ったかが実感できます。完成後1年もたたずに病死した一葉は、まさに命を削りながらこの作品を創り上げたのではないでしょうか。このような名作で、自分のルーツともいえる母が育った環境を垣間見ることができ、ウォーキングを楽しむことができたのは幸運でした。